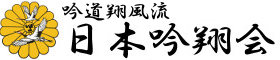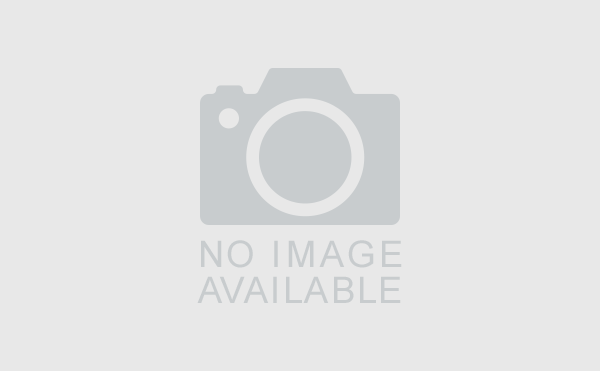令和6年度「漢詩碑顕彰祭」
令和6年度 第十三回「漢詩碑顕彰祭」に参列して 育英支部 小林剣風
令和六年十月二十五日、第十三回「漢詩碑顕彰祭」並びに吉川経家公の四百四十四年忌法要が執り行われました。
吟道翔風流日本吟翔会からは、佐藤宗家会長、春菜副会長を始め、師範の先生、若桜、岩美、文化、青谷、育英、賀露、城北、瑞穂の各支部から二十三名が参列。
午後二時からの真教寺での法要では、初代佐藤翔風宗家の創作された「久松山懐古」を奉吟し、三時からは、久松公園のお堀端の漢詩碑の前で同詩を合吟しました。
今回顕彰祭に参列するに当たり、吉川経家のことを少し調べてみました。
吉川経家は、千五百四十七年毛利の家臣で石見地方を治めていた吉川経安の嫡男として生まれました。羽紫秀吉の侵攻から毛利を防衛すべく、最前線であった鳥取城に派遣されたのは、千五百八十一年(天正九年)。三月に入城。しかしながら当時は既に秀吉により、兵糧米が高値で買い占められており、兵糧を手に入れることは困難な状況でありました。
毛利軍の中にこの困難な状況下で、任務に赴く武将は他にいなかったと思われます。同年七月には秀吉が二万の兵を率いて鳥取城を包囲、この時場内の兵糧は僅か一か月分。人馬や植物、樹の根まで食べて頑張ったが、三か月目には餓死者が出始め、ついに籠城四か月日に城兵の助命を条件に降伏。十月二十五日に家臣の静間源兵衛の介錯により自刃を遂げました。享年三十五歳。
戦う前に、兵糧尽き果て悲壮な最期だったと思います。初代宗家が漢詩「久松山懐古」の最後に書かれている「節義誠忠萬世伝」無念ではあるが、忠義を尽くすこの生き様に心打たれる血潮を感じずにはいられません。
後日、 一人でニノ丸に上がり、四百四十四年前の状況を思い浮かべながら、暫しベンチに佇んでいました。
余談になりますが、笑点の司会を務めていた五代目三遊亭園楽は、吉川経家の子孫に当たります。